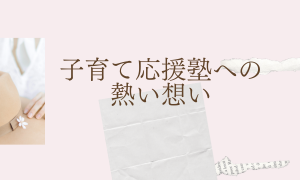45年間のライフストーリー
「弟を失ったあの日」
1歳半下の弟は生まれつき脳の機能に異常があり、
産まれてすぐ入退院を繰り返していました。
弟が生まれる前のわたしは、
母にぴったりとくっついて離れない甘えん坊だったそうです。
けれど弟が生まれてからは、母は病院に行くことが多くなり、
わたしは祖母や父と過ごす時間が増えました。
それでも泣きもせず、ぐずりもせず、
とても大人しく “いい子” に留守番をしていたと聞いています。
そして、わたしが3歳のある日、事件が起きました。
その日は、冬の夕方だったように記憶しています。
居間で弟と二人きり。
弟は床に座り、小さなおもちゃのピアノを指でたたいていました。
その横へ、わたしは近づいていき——
そこで記憶は途切れます。
再びつながるのは、その次の瞬間。
床に転がった弟が、大きな声で泣き叫び、台所で夕飯を作っていた両親が、
急いで駆け寄ってくる——
わたしの記憶は、そこで止まっています。
あのあと、弟は救急車で運ばれ、そのまま帰ってはきませんでした。
「大好きなママにほめられたくて」
弟の死から2年以上が過ぎ、
わたしが5歳になったころ。
母とお風呂に入り、そろそろ寝ようとしていたとき、
玄関から父の声が響きました。
「エレクトーンが来たぞ〜!」
外を見ると、父のグレーのワゴン車。
荷台のドアが跳ね上がると、
家具のように大きなオルガンが積まれていました。
眠気は一瞬で吹き飛んで、裸足のまま駆け寄り、
鍵盤を片っ端から叩き、足踏みペダルを面白くて何度もパタパタさせました。
「そろそろ寝なさい!」
母の声も、このときばかりは耳に入らず…
白い鍵盤を押すたびに、
胸の奥のワクワクは止まりませんでした。
簡単な曲は、すぐに弾いてしまうわたしをみて、
母は才能があると思ったようで、
すぐにピアノ教室を探してきてくれました。
テキストは次々に進み、ご褒美シール帳はすぐに一杯。
でも、シールをもらうよりも、そのノートを母に見せ、
「すごいね!」と頭を撫でてもらうほうが、
嬉しくてたまりませんでした。
ある日、先生が、
「この子は才能ありますよ、お母さん!」
帰宅後、母は嬉しそうに言いました。
「将来、ピアノの先生だ!」
その言葉を丸ごと飲み込み、
その日から、それが”自分の夢“だと信じました。
「やりたいことがない罪悪感」
その頃のわたしは、ぜんそくを患っていました。
夜になると頻繁に咳き込み、喉が細く締まっていく。
息を吸うたびに全身の筋肉を使うほど力が入り、
窓から隙間風が吹き込むみたいに、
「ヒュー」という音が喉の奥で鳴るのです。
発作は夜中に出ることが多く、
一晩中、母は布団の横で背中をさすってくれました。
しんどくて母の身体にもたれかかると、
そのぬくもりが伝わり、それだけで少し楽になる。
「早く治まりますように」
母の声は子守歌みたいで、その声に包まれるうちに、
いつの間にか眠ってしまうこともありました。
小学校に上がる頃には発作がさらにひどくなり、
病院を転々とする日々。
そんなある日、
近所の人が「良い専門病院がある」と教えてくれ、
母とふたりで行くことに。
内診と血液検査を終えると、
医師と母はしばらくカウンセリング室で話し込んでいました。
部屋を出たあと、薬の匂いが充満した待合室の硬いベンチに座り、
母が真剣な顔で言いました。
「退屈になっちゃダメなんだって。ぼーっとしたら発作が出るってことなんだよ!」
ぜんそくは、刺激がない状態だと自律神経が乱れやすくなり、
発作が起きやすくなる病気だそうです。
それから、母と一緒に“やりたいこと探し”が始まりました。
漫画を買ってきてくれたり、ビーズでネックレスを一緒に作ったり…。
けれど、どれも長くは続かず。
発作が出るたびに、
「わたしには“やりたいこと”がないからダメなんだ…」
「またママを悲しませちゃった…」
そうやって自分を責め続けていました。
その後もこれといった“やりたいこと”は見つからなかったものの、
ぜんそくの発作はいつしか少しずつ落ち着いていったのです。
「わたしの進路」
ピアノの曲がどんどん難しくなり、
オルガンではもう追いつかなくなった頃、
両親がアップライトピアノを買ってくれました。
オルガンとは違い、音も響きもタッチも、すべてが重厚。
学校から帰ると真っ先にピアノに向かう――
それが日課であり、いちばんの楽しみでした。
中学二年の冬。
進路の話がちらほら出始めた頃、母がふと口にしました。
「音大を目指そうか?」
その言葉に、わたしは何の疑いもなく大きく頷き、
後日、母と二人でピアノ教室へ。
冬の夕方、外はすでに暗く、
レッスン室の窓ガラスには反射した自分たちの姿。
黒光りするアップライトの前に先生が座り、
わたしと母はベンチに腰を下ろしました。
「この子を音大に入れたいのですが…」
その瞬間、先生の表情がほんの一瞬だけ固まり、
少しの沈黙のあと、静かに告げられました。
「正直に申し上げると、このままでは難しいです」
その言葉を聞いた瞬間、
――え…じゃあ、先生が言っていた“才能がある”って、
あれは何だったの?
思わず口からこぼれそうになるのをこらえ、
膝の上で楽譜の角を強く握りしめ、ただ黙っていました。
続けて先生はこう言いました。
「ただ、今からでも毎日三時間以上、
専門の指導に切り替えて徹底的にやれば、
狙えない話ではありません」
道がゼロではないと知り、ほんの少し安堵したものの、
簡単に行けると思っていただけに、ショックは大きかった。
母の気持ちはもう決まっていたのでしょう。
「この子はピアノが好きみたいなので、
やれるところまでお願いします」
そう先生に頭を下げました。
その日から、
生活の軸ははっきりと「音大に向けた練習」へと
切り替わっていきました。
中学三年のとき、担任の先生に進路を相談すると、
「ピアノの環境を考えるなら、大学が上にある私立の高校がいい。
音大がダメでも、そちらに進めますから」
その言葉に背中を押され、私は私立高校へ進学することにしたのです。
「初めての挫折」
毎日、学校から帰るとすぐに着替え、ピアノの前に座る。
夕食までの数時間、ひたすら鍵盤に向かう生活が続きました。
メトロノームの「カチ、カチ」という音が部屋を支配し、
徹底的に基礎練習。
もはや“楽しさ”は微塵もなく、ただノルマをこなす日々。
それでも、不思議と「嫌だ」とも「やめたい」とも思いませんでした。
――「春休みに音大の先生に一度見てもらいましょう」
高校三年生になる前、ピアノの先生からそう告げられ、
期待と不安の入り混じった心で、その日を迎えました。
案内されたのは、大学の一角にあるレッスン室。
重厚な扉を開けると、中央には黒いグランドピアノが一台。
鍵盤の前に椅子が二脚並び、防音室のせいか、部屋は静まり返っていました。
自分の心臓の音が、はっきりと聞こえるほど。
その静けさが、緊張をさらに膨らませていきました。
挨拶は簡単に済まされ、形式的な言葉のあとで、
「では、弾いてください」
深呼吸をひとつして椅子に腰を下ろし、鍵盤に手を置く。
音を出した瞬間――
「違う。そこは〇〇〇」
教授の声は、何の温もりも感じられませんでした。
まるで、不良品を見つけたときに淡々と指摘するような、
事務的で冷たい声。
「ストップ」「違いますね」「もう一回」
その三言が繰り返されるたびに、顔だけが熱く、
指先はどんどん冷たくなっていきました。
一時間のレッスンが終わるころ、教授は一言だけ言いました。
「あなたは、どうしてここにいるのですか?」
まるで「場違いだ」と告げられたような、その言葉。
頭を殴られたように視界が真っ暗になり、
一秒でも早く、この場所から消えたくなりました。
震える声で「ありがとうございました」とだけ言い、
逃げるように扉を出て、廊下の突き当たりのトイレに駆け込みました。
個室の鍵をかけた瞬間、堪えていた涙が溢れました。
小さな窓の外に見えるグランドピアノを横目に、
「もう、ここに来ることは二度とないな」
そう確信したのです。
悔しさ、恥ずかしさ、絶望感。
「なんで、わたしはここにいるんだろう…」
しばらくのあいだ、動くこともできませんでした。
その後、どうやって帰ったのか、何を感じていたのか、記憶はありません。
家に帰り、母に一部始終を話すと、
「やるだけやったんだから、えらかったよ」
母はそう言って、わたしをねぎらってくれました。
数日後、再び先生のもとを訪ねると、
「もう一段階、レベルを下げれば入れる音大があります」
その言葉は、まるであらかじめ用意されていたかのように淡々とした口調で、
そして、こうも聞こえました。
――「お金を払えば誰でも入れる音大です」
家に戻り、ひとり静かに考えました。
「無理して音大に行くことはない。上の短大にしよう」
「保育士ならピアノも生かせるし」
母も納得してくれました。
「保育科のある高校にしておいて、よかったね」
その瞬間、どこかホッとしている自分がいました。
その後、ピアノ教室に行き、保育科に進むことを伝えると、
「では、ヤマハの講師を目指しましょう」
幼いころからグレード資格を取っていたので、
順調に進めば講師も十分狙える、と先生は軽やかに告げました。
こうして、再びピアノ漬けの生活が始まったのです。
「ようやく出た本音」
短大に無事入学し、授業が始まると、
その内容は想像していた以上におもしろいものでした。
なかでも心を掴まれたのは、幼児心理学や発達心理学の授業です。
“心”というものに、仕組みや法則があると知ったとき、
その構造を知っていく過程が、たまらなく面白く、新鮮でした。
必須ではなかった臨床心理学も履修し、
どんどんのめり込み、気づけば毎回の講義に夢中。
授業だけでは物足りなさを感じ、
それがきっかけで本をよく読むようになりました。
しかしその一方で、なぜか仲間には馴染めなかった。
純粋に学生生活を楽しんでいる同級生たちが、
どこか幼く見えていました。
ちょっとしたことで大笑いして、
他大学のサークルとコンパに行って、
恋愛話で盛り上がって——
最初の頃はとりあえず合わせて、
サークルにも入り、合コンにも顔を出していましたが、
何ひとつ楽しいと思えず、ただ疲れるだけ。
気づけば、授業も、学食も、空き時間も、
周りにはいつも誰もいない。
生まれて初めて、「疎外感」というものを味わった2年間でした。
「みんなとは目指す場所が違うから合わないだけ」
「わたしはその間も、ちゃんとピアノを練習してる」
「浮ついて遊んでいる人たちとは違う。わたしはちゃんとしてる」
そうやって 優越感を抱きながら、
馴染めない現実をごまかしていました。
救いだったのは、短大にある個室のピアノ練習室。
扉を閉めてしまえば世界から切り離され、
その小さな空間で、寂しさを埋めるようにピアノに没頭していました。
しかし、卒業までに講師資格は取れず、
そのまま幼稚園に就職。
仕事は忙しく、ピアノに触れる時間は減り、
レッスンも少しずつ足が遠のいていきました。
そんなある日、ピアノの先生から突然の知らせが。
「結婚して関東に行くことになりました。
他の先生に引き継ぐので、そのまま頑張ってくださいね」
帰宅後、その話を母にすると、
「ずっと信頼してついてきたのに、捨てられた!」
母は激しく怒りました。
そのときのわたしも母に同調していたのですが——
部屋に戻り、ベッドに仰向けになった途端、
頭の中で、言葉が湧いて出てきました。
「そうだよ、悪いのは先生だよね!」
「充分やった。もういいよね!」
「これでピアノをやめられる!」
ようやく本音が出たのです。
今までの苦労や積み重ねたことなど、
どうでもよくなっていました。
ただただ、嬉しさと解放感。
その後、母にはただ一言だけ、
「仕事が忙しくて、もう続けられない」
母はそれ以上何も言いませんでした。
こうして、ピアノから解放されました。
「結婚話が、わたしを揺らし始めた」
ピアノを手放した数年間、まるで羽の生えた鳥のように、
思いきり遊び回っていました。
幼稚園の同期と気が合い、アイドルのコンサートに通い、
叫び、歌い、飛び跳ねる。
県外まで遠征し、旅行して、ショッピングして、
夜更けまで笑い転げる。
「ピアノに縛られていないって、こんなに楽なんだ」
その感覚が、体の奥深くまで沁み込んでいきました。
やがて就職して三年目、二十三歳。
幼稚園の仕事にも慣れ、子どもたちに慕われ、
保護者にも感謝され、上司にも認められるようになっていました。
そのころから、母の口から“結婚”という言葉が出るようになったのです。
「いい人いないの?」
「お母さんは二十三歳で結婚したから、あなたもそろそろ」
そのたびに、胸の奥がざわつきました。
「いい人なんて、いるわけないじゃん」
「まだ結婚なんて、考えられない」
そう言いたい気持ちを飲み込み、
笑ってごまかしたり、話を逸らしたりしていました。
確かに、同級生の中には結婚する友達もちらほら。
わたしも「いつかは結婚するんだろう」と思ってはいたけれど、そ
れはまだ自分とは無関係の、遠い未来の出来事のように感じていたのです。
「まさか、母の口から“結婚”という言葉が出るなんて…」
それは、よくある“うっとうしい”とか“お節介”とは違いました。
そのときわたしが感じたのは、“見捨てられた”という感覚。
自分でも「なんかおかしい」と分かるほどの、
説明のつかない違和感が胸に残りました。
「結婚しなくてもいい方法って、ないのかな?」
気づけば、そんなことを考えるようになっていたのです。
ある日、仕事帰りにお気に入りの雑貨店へ立ち寄ると、
そこには、幼稚園を辞めた先輩が店員として立っていました。
かつては声をかけるのも怖いほどクールだった人が、
柔らかい物腰で微笑んでいて、まるで別人のように輝いて見えました。
何度か通ううちに距離が縮まり、ある夜、一緒に食事をしたときのこと。
彼女は言いました。
「いつか、自分のカフェを開きたいんだよね」
迷いのない声で、未来をまっすぐに語るその姿が、まぶしくて、羨ましくて。
会うたびに、わたしの心も少しずつ動き出していきました。
「もっと何かに挑戦したい」
「違う仕事をしてみたい」
そもそも、強い意志で保育士を選んだわけではなかった。
ピアノを活かせるからと、“流れで入った保育科”。
そのまま“流れで就職した幼稚園”。
――そう気づいてしまった瞬間から、
どうすれば辞められるかばかり考えていました。
「じゃあ、わたしは何がやりたいの?」
その問いが、頭の中で何度も繰り返される。
答えが見つからないまま日々を過ごしていた、
ある夜のことです。
お風呂上がり、ソファに沈み込んだ瞬間、
ふと浮かび上がったのは幼い頃の記憶でした。
母が読んでいたインテリア雑誌のページをめくりながら、
理想の部屋を空想していた時間。
父はDIY、母は模様替えや整理整頓が大好きで、
家族総動員で部屋の改装をしたこと。
テレビのインテリア特集を録画して、母と一緒に何度も観たこと。
「インテリアコーディネーター、やりたいかも!」
勢いのまま、資料を請求しました。
「休日に通えるなら働きながらでもいける」
「働きながらなら両親も反対しない」
―そしてこれなら、母も許してくれるはず。
家族会議の末、父はこう言いました。
「自分で稼いだお金でやるなら、やってみたらいい」
母も了承してくれましたが、そのとき、小さくつぶやきました。
「結婚は遠のいたか…」
その一言で、はっきり母の期待から外れたのだと分かりました。
やってもいいけれど、正解ではない――
線を引かれたような感覚が胸に残りました。
こうして、幼稚園で働きながら、
休日はカルチャースクールへ通う生活が始まりました。
「インテリアコーディネーターを目指して」
休日は勉強、平日は幼稚園、夜もまた勉強。
生活は確実に忙しくなったのに、
不思議と満たされていました。
建築用語が少しずつ耳に馴染み、
図面も少しずつ引けるようになる。
できることが増えていく感覚が、
何よりも心地よかったのです。
半年後、インテリアコーディネーターの試験に挑戦し、
基礎編に無事合格。
けれど、実務経験がないため応用編は受けられず、
資格の取得は翌年以降に持ち越しとなりました。
そこで、わたしは平日の午前中に授業のある専門学校を選びました。
つまり、その時点で、幼稚園を続ける選択肢を、
自分の手で消したのです。
表向きの理由はこうでした。
「もっと技術を磨きたい」
「今の学びだけでは足りない」
けれど本当は、幼稚園を辞める“理由”が欲しかった。
早く切り替えてしまいたかったのです。
そして、区切りのいいタイミングで幼稚園を退職し、
業界でも有名なインテリア専門学校へ進むことを決意しました。
専門学校での二年間は、とにかくハードでした。
クラスの多くは建築や美術の経験者。
最初は不安しかなかったけれど、
持ち前の努力で、気づけば夜中まで課題をこなす毎日。
必死でくらいつき、なんとかついていきました。
そして卒業後、
ハウスメーカーのインテリアコーディネーターとして
就職が決まったとき、好きなことを仕事にできる、
その嬉しさで胸がいっぱいでした。
インテリアに囲まれて働けることが、
ただそれだけで幸せだったのです。
「やりたいことをやったはずなのに…」
配属は、インテリアショップの店員兼、住宅のコーディネーター。
北欧インテリアに囲まれ、
カフェのようなBGMを聴きながらガラス越しの街路樹を見る。
まさに思い描いていた職場。
人間関係にも恵まれ、刺激的で楽しい毎日。
しかし、状況は目まぐるしく変わっていきました。
先輩が次々と辞め、2年ほど経つと、
いつの間にか私が一番のベテランに。
そこから、仕事が一気に増えました。
モデルルームのコーディネート、高額な注文住宅の案件。
2年目の私には明らかに荷が重い仕事ばかり。
断ることもできたのに、
「期待に応えて、もっと認められたい!」
そう思って次々引き受けてしまいました。
最初は燃えていましたが、やがてキャパオーバー。
仕事が回らず、失敗が重なり、自信を失い、
とうとう職場へ行けなくなってしまいました。
当時の上司は、薄々気づいていたのでしょう。
「とりあえず一週間休んでください」
そう言ってくださいました。
一週間、自分を振り返りながら、のんびり過ごすと、
気持ちは少しだけ楽になっていきました。
「できない仕事は断ろう」
と分かっていながら、もう一方で、
「もっと認めてもらうまで頑張ろう」
そう思っている自分もいました。
そして、一週間後に出勤。
ところがその直後、
「ショップは閉店。インテリア部門を営業に吸収する」
との通達があり、
人員削減や仕事内容の大幅な変更の話が持ち上がりました。
「いいタイミングかもしれない」
しばらく悩んだ結果、辞表を提出。
けれど、続ける選択肢もあったのに途中で投げ出してしまったような、
嫌な感覚が残りました。
「あんなに頑張って勉強したのに…」
「インテリアも、本当にやりたいことじゃなかったのかもしれない…」
考えれば考えるほど、頭の中がざわついていきました。
ピアノもそうだった。
保育士もそうだった。
始めたときは楽しくて、夢中になって、心からやりたいと思っていた。
なのに――気づくと息が詰まって苦しくなる。
続けるのがしんどくなってしまう…。
「これは一体、何なんだ?」
「わたしは本当は、何がしたかったの?」
「やりたいことのはずだったのに、どうして毎回こうなるの?」
答えのない問いだけが膨らみ続け、
そのたびに自分自身を責め続けました。
「やりたいことが、分からない…」
情けなさと混乱が、同時に襲ってきました。
「休んだ先に、次の人生が待っていた」
がむしゃらに走り続けてきた自分を振り返り、
いったん立ち止まることにしました。
旅行に出かけたり、本を読んだり、ヨガや瞑想で心と身体を整えたり…。
半年の自由は、まさに「回復期間」でした。
好きなことをして、好きな人と会って、
何にも追われない時間を味わったことで、
心の底がようやく静かに満ちていきました。
そんな、すっかり力が抜けた頃、
カルチャースクールで出会っていた彼と偶然再会しました。
付き合い始めてすぐ、言葉にされる前から
「この人と結婚するんだろうな」
と不思議と思えました。
そう思えた瞬間、自然と自分の働き方が決まっていきました。
インテリアの仕事に戻るのは正直怖かった。
また失敗して、また投げ出して、
また自分を嫌いになる気がしたから。
だから私は、自信のある“保育”へ戻ることを選びました。
時間に余裕のある「子育て支援センターの時短パート」に。
その頃から、母は
「彼とはいつ結婚するの?」
「お互い、いい歳なんだから」
そう急かされるようになりました。
確かに、母の言うことも正しいし、
わたしも結婚するなら彼しかいないと思っていました。
自然や旅好き、音楽の好み、笑いのツボ。
その「合う」という感覚は、日常の端々に現れていました。
夕焼けを見たとき、同じタイミングで「きれいだね」と声が重なること。
ドライブで流れる曲が、偶然にもわたしの好きなものばかりだったこと。
ドラマを観て、同じところで笑い、同じところで泣けたこと。
人前では仕事をバリバリこなす彼が、
わたしの前では涙を浮かべる繊細さを見せる、
その落差が愛おしいと思えたこと。
そういう “一致” が積み重なって、
わたしはこの人とならと思えたのです。
そして何より――
彼と一緒にいる安心感は、母のそばにいるときの感覚に近いものがありました。
だから結婚の話題も、わたしのほうから切り出すことが増えていきました。
彼を選べば、母も喜ぶ。
そう思っている自分がいました。
そうして彼はプロポーズしてくれて、結婚が決まり、新しい生活が始まりました。
「完璧の正体に気づいた日」
幸せなはじまりのはずなのに、
わたしは毎日、ノルマを消化するように生活していました。
料理も掃除も仕事も、手を抜かない。
疲れていても三食手作り、掃除は毎日隅々まで。
それが当然だと思い込んでいました。
夫は本当にやさしく、手を抜いたって文句を言う人ではありません。
それなのに――
何かが乗り移ったように、完璧さを求めて、
ひたすら走り続けていきました。
そんなある朝、
目を開けて身体を起こそうとした瞬間、
腰の奥に鋭い痛みが走り、息が止まりました。
「……え?」
再び起き上がろうとすると、電流のような痺れが全身を走り、
声も出ず、横向きのまま動けませんでした。
頭では「仕事に行かなきゃ」「家事しなきゃ」と命令しているのに、
体はブレーキをかけられたように動かない。
ようやく治療で痛みは引いたものの、
少し荷物を持つだけで腰を痛める体になってしまいました。
ちょうどそのころ――
「子どもも欲しいし、これを機に仕事は辞めようかな」
ふと浮かんだその考えを夫に伝えると、
「それがいいと思うよ。体が資本だから」
と即答で背中を押してくれました。
その言葉を聞いた瞬間、迷いは消え、 仕事を辞めました。
仕事をやめてからは、腰に良いと聞いたウォーキングをしたり、
休みの日には二人で釣りに出かけたりするうちに、身体も心も少しずつ元気に。
そして、久しぶりに本を開くことができたのです。
ずっと余裕がなくて読む気力もなかったのに、
ようやく文字が頭に入ってくる感覚が戻ってきました。
タイトルは思い出せませんが、精神世界の本。
ページを追ううちに、ある気づきが浮かび上がってきました。
母のように”完璧に家事をこなさなければいけない”と思っていたことに。
整った台所。
隙なく回る家事。
何一つ手を抜かない母の姿。
それが “正解” だと無意識に刷り込んでいたことに気がついたのです。
「だから苦しかったのか…」
「わたしは、母になろうとしていたんだ」
気づきの後、疲れた日は、インスタントを使い、
外食にも気軽に行けるようになり、
“てきとうに” を自分に許す暮らしへと変わっていきました。
不思議なことに、家事の手を抜けば抜くほど、
夫は喜び、会話も笑顔も増えて、家庭は前よりずっと穏やかに。
「これで、もう母に縛られることはない!」
「わたしはようやく自由になれた!」
そのときのわたしは、そう信じていました。
そして、しばらくして妊娠が分かりました。
「異常なわたし」
長年の保育士の経験もあり、子育てには自信がありました。
ただ、
「お腹の中に赤ちゃんがいる…」
なぜか、心の底から喜べませんでした。
頭では「嬉しいこと」と分かっているのに、
感情だけがどこか遠くに置き去りにされているような感覚。
「お腹の赤ちゃんが愛おしくてたまらない」
本来はそう思えるのが自然なはずなのに、わたしは心の底から喜べない。
「これはおかしい…」
「異常だ」
それを打ち消すように、
「産まれたら、きっと愛おしくなるはず!」
そう言い聞かせました。
そして、ベビー用品を作ることに没頭。
おくるみを編み、授乳用のクッションを縫い、母子手帳カバーを作り―
次々と自分の手で用意していきました。
手を動かして“母親らしいこと”をすることで、
まるで「母になる自分」を証明しようとしているかのように。
そして、その「異常さ」は、出産直後に、
もっと冷たい形で姿を現したのです。
「やはり、愛おしいと思えない…」
息子は予定より一ヶ月以上早く生まれ、
未熟児のため、保育器の中にいました。
別室で、透明な箱の中。
小さな体はチューブにつながれ、
静かに眠っています。
夜の授乳の時間になると、
薄暗い病室で非常灯だけがぼんやり光る。
ベッドの上で、深く息をつき、
「行かなきゃ…」
義務のように、眠く気だるい身体を起こし、
静まり返った廊下へ無言のまま歩いていきました。
保育器の前に立っても、
透明な壁の向こうで小さな手がかすかに動くのを見ても、
感情は何も動かない。
その「何も感じない自分」に、戸惑いました。
授乳の時に抱っこをしても、温もりを感じても、わたしの心は静かなまま。
「やはり、異常だ」
しかし、それを認めるわけにはいかないので、
「産後だし、疲れてるだけ」
「突然だったから、まだ実感が湧かないだけ」
そうやって理由を並べて、考えないように蓋をしました。
そして退院の日。
家に戻った瞬間、全身の緊張がふっと解けました。
「やっぱり産院の環境が悪かっただけか…」
無機質な部屋でもなく、保育器の前でもなく、
生活の匂いが残る “自分の場所” に戻れたことで、
気持ちは安定しました。
その後、息子を見て「かわいいかどうか」という感情は、
自分でも意識の外へ押し出していたように思います。
育児の忙しさに紛れたのか、
わざと考えないようにしていたのか――。
夜中の授乳や細切れ睡眠は確かに大変でしたが、
「赤ちゃんがいればこれが普通だ」と思っていたので、
そこに違和感は覚えませんでした。
「努力しても報われない子育て」
息子が1歳半を過ぎ、
自由に歩き始めた頃から状況は一変しました。
「なんでママの言うことを聞かないの!」
「やっても、やっても家事が終わらない!!」
子育てを楽しむどころか、苦痛と苛立ちの毎日。
着替えさせようとすれば逃げ回り、
食事を出せば投げられ、
外に出れば走り出し、
抱き上げれば反り返って泣き叫ぶ。
そのひとつひとつは、
子育ての本にも書いてある “よくあること” なのでしょう。
でもそれが、朝から夜まで、毎日途切れず続くという現実は
、「よくあること」では飲み込めないものでした。
土日は、夫が家事も育児も助けてくれたので、
まだ余裕はありました。
しかし平日になると、一気に地獄に引き戻される。
さらに追い打ちをかけたのは、
「他のママ達は楽しそうに見える」という現実でした。
公園ではレジャーシートを敷き、
笑いながらピクニックしている親子たち。
児童館では先生の話を聞き、
ママの膝に座っていられる同じ月齢の子どもたち。
支援センターでは、後から来たママたちが、
あっという間に打ち解けて会話している。
わたしはその輪に入る余裕すらないまま、
走り回る息子を追って部屋じゅうを移動するだけ。
「どうして、私だけ…」
そして訪れた三歳児健診。
「発達に遅れがある」と指摘されました。
保育園への単独通園は見送りとなり、
代わりに、親子で通う療育施設に通うことに。
つまりーー
引き続き、平日は朝から晩まで、
わたしと息子の二人きり。
ひとりの時間はさらに奪われ、
息つく暇もない日々がその先に見えました。
わたしは、どこまで虐げられるんだ――。
そして想像を超えた日々が始まりました。
療育での息子は、ひとりだけ輪の中に入れない。
戻そうとすると髪をひっぱられ、泣き叫ぶ。
手作りのお弁当は、全く口をつけない。
療育に通えば少しは楽になると思っていたのに、
むしろ、できない息子を直視しなければいけない現実に、
ほとほと疲れていきました。
でも、息子を放置していたわけではありません。
わたしなりに精一杯、関わっていました。
ふれあい遊びもした。
絵本も読んだ。
散歩だって、毎日、何時間も一緒に歩いた。
やれることは全部やった。
それでも、何ひとつ報われない。
「なんで、こんなに苦しまなきゃいけないの?」
これまでの人生は、自分が頑張れば何とかなってきた。
なのに子育ては、頑張っても頑張っても報われない。
「もう無理かも…」
声にはならなかったけれど、
その感覚だけがじわじわと心を支配していきました。
「母親失格だ」
そしてある日、ついに “限界” が訪れました。
マンションのエレベーターに乗りたいと何度もせがみ、
わたしの髪を引っ張る息子を抱え、
ぐったりした腕でなんとか家に戻りました。
玄関を開けた瞬間、床に寝転び、
いつになく激しく泣き叫ぶ息子。
冷静を装い、
洗濯物を取り込もうとベランダに向かった
そのとき——
喉の奥で何かがひっかかるような、
聞いたことのない低い唸り声が…
それは、わたしの声でした。
息子に向かって暴言を吐いていたのです。
その瞬間、何かのスイッチが入り、
制御が外れ、床にあった何かを蹴り、
それでも収まらず、息
子を叩いていました。
その瞬間、我に返りました。
「母親失格だ…」
全身の力が抜け、寝室へふらつくように移動し、
そのままベッドに倒れ込みました。
身体がベッドに沈む感覚と同時に、
得体の知れない自分の“本性”に底知れね恐ろしさが湧き起こり、
身動きが取れませんでした。
しばらくして息子が気になり、
足音を殺してリビングをのぞくと、
癇癪はすでに止まり、
何事もなかったかのようにテレビを見ているのです。
「怒鳴られ、叩かれたのに、泣きもしないんだ」
「ママの姿が見えなくても、探さないんだ」
その瞬間、頭をよぎったのは――
「愛情がないことが、息子に伝わっているのかもしれない」
そう思った途端、“母親失格”という烙印が
さらに濃く押しつけられたようでした。
まるで、息子に突き放されたような、
見限られたような、深い絶望感。
それでも、日常は容赦なく続きます。
ご飯を作り、療育に行き、寝かせる。
体は動いているのに、
心だけが出口のない迷路をさまよい続けていました。
ある日、またイライラが溢れた瞬間、
スイッチが入る前にカバンと息子を抱えて無言で車に飛び乗り、
母の元へ向かいました。
「このままでは、息子と死んでしまいそう!!」
呼吸を乱しながら訴えると、母は言いました。
「何バカなこと言ってるの!」
「しっかりしなさい!お母さんでしょ!」
一番、聞きたくなかった言葉でした。
その瞬間、はっきりと分かった。
「認められたかった」のだと。
「あなたはよく頑張ってるよ」
ただ、その一言が欲しかったのです。
“母親としての私” を、母に肯定してほしかった。
「この辛さ、死んだら分かってもらえるかもしれない」
クローゼットのパイプや物干し竿にロープをかける映像が、
頭の中で静かに再生されるようになりました。
そんな極限状態の中、
しばらくして、さらなる悲劇が襲いました。
夫が突然倒れ、わずか10日後、帰らぬ人となったのです。
息子の5歳の誕生日を目前にしてのことでした。
「息子と生きていく」
夫の死。
あまりに突然のことで、
現実がまったく飲み込めないはずなのに、
なぜか私は妙に冷静でした。
「ここで崩れたら、母を心配させてしまう」
その思いが、感情を奥深くに押し込めていたのです。
頭の中は、現実的なことでいっぱい。
葬儀の手配、息子を誰に預けるか、
どの時間に迎えに行くか、
どこに連絡をすればいいのか――。
涙よりも先に、「どう動くか」ばかりを考えていました。
やらなければならないことを、ひとつひとつ淡々とこなしていく。
目の前で起きているのに、
まるで自分が自分を外側から見ているようでした。
感情のない“もうひとりの私”が、淡々と動いている
――そんな感覚。
悲しいはずなのに、涙が出ない。
泣くことさえ、許されない気がしていました。
葬儀の段取り、喪主のあいさつ、
役所での手続き、親族への連絡、
香典返し、書類の整理――。
次々とやるべきことが頭の中を占めていきました。
親族の前では笑顔で応対し、
母の前では平気なふりを崩さず、
泣き顔を見せませんでした。
けれど、誰もいなくなると、
寂しさや虚無感が嵐のように襲いかかるのです。
布団に横になると、
沈黙と闇がその感情をさらにおびき寄せ、
涙が勝手にあふれて止まらない。
台所で洗い物をしようと水を出しただけで、
喉が詰まり、呼吸が苦しくなり、
その場に崩れ落ちるようにうずくまり、
しばらく嗚咽。
泣くことを止められない時間と、
平気なふりをし続ける時間が、一
日の中で交互に訪れていました。
「なんで夫だったんだろう…」
「わたしが先に逝った方が、息子のためにも良かったのに…」
そんな思いが、波のように押しては引いていく。
それでも、朝は来て、また夜が訪れる。
四十九日の法要が終わった午後、
息子と手をつなぎ、家の近くをゆっくり歩いていました。
夫と三人で何度も歩いた、いつもの公園。
芽吹き始めた若い緑の桜の木の下に、
影が二つだけ並んで伸びていました。
「今まで、当たり前に3人一緒だったのに…」
「全部放り投げて逝っちゃうなんて、ズルいな…」
気づけば、涙が頬をつたっていました。
そのときです。
「息子と生きるのは、わたしなのか!」
突然、「ああ、そういうことか」と、
胸の奥の何かがスッと抜けていきました。
「この子と生きていくのは、わたしだったのか」
「息子と生きていくしかないんだな」
不思議な感覚でした。
けれど、最初からそう決まっていたような――
わたしがこの役目に選ばれたような感覚が、
じわじわと広がっていきました。
その瞬間から、“生きること”という方向へ目が向き、
息子と二人で、これからどう生きていくのかを考えるようになりました。
「揺れ動く気持ち」
「これからは、息子と平和に、しあわせに暮らしたい」
「もう、この地獄の連鎖を終わらせたい」
そう強く願いながら、これからのことを考えました。
ひとりで抱え込まず、親に頼ることを選ぼう――。
そう思った瞬間、胸の奥がざわつきました。
「でも、本当に頼っていいの?」
心の奥で、母の声が響き続けていました。
まるで呪文のように、幼いころから何度も繰り返し聞いてきた言葉。
「まめちゃんは、依頼心が強いからね」
その言葉は、「自分でやらなきゃ」という掟になっていました。
“人に頼ることはよくないこと”
“ひとりで頑張らなきゃいけない”――
いつの間にか、そんなふうに信じ込んでいたのです。
けれど、恐れもありました。
また、二人きりになったらどうなるんだろう。
疲れや孤独が重なったとき、あのスイッチが入って、息子に手をあげてしまうんじゃないか――。
そんな自分を想像するだけで、怖くてたまらなくなりました。
だからこそ、親に助けてもらおう――そう思いました。
母からの掟を守るより、自分と息子の身を守ることを選ぼう。
そして、わたしは実家に戻ることを決意したのです。
「親との同居生活」
親との同居が始まり、哀しみが消えたわけではないけれど、会話のある生活のおかげで、少しずつ心が安定していきました。
息子とのバタバタの生活も目に見えて整い始め、いっぱいいっぱいだった毎日は終わり、体力も思考も、少しずつ回復に。
「一人じゃないだけで、こんなに楽になるのか…」
一日が終わるたびに、その実感がじわりと増していきました。
暮らしが落ち着き始めたその頃、ちょうど息子は6歳。
就学を前に、医療機関で発達検査を受けることになりました。
診断名は“中度知的障がいを伴う自閉症”。
言葉も出ず、同じ月齢の子と比べても明らかに発達が遅れていたので、何らかの障がいが告げられる覚悟はついていました。
しかし、一番ついてほしくなかった「知的障がい」という文字を目にした瞬間、 目の前が揺れました。
それでも心のどこかで、
「この先の成長で軽くなるかもしれない」
「障がいという言葉が外れる日が来るかもしれない」
そんなわずかな期待が、まだ残っていました。
そのわずかな期待があったからこそ、
「とにかく今は、目の前のことをやっていくしかない」
そう自分に言い聞かせることができたのだと思います。
そうして気持ちを切り替えました。
ちょうどそのとき、息子と通っていた療育施設の園長先生から、「保育士として働かないか」と声をかけていただきました。
自分にも息子にもプラスになると思い、働くことを決意したのです。
「また同じ場所に戻っていく感覚」
療育施設で働くようになったことで、保育を一から学び直す機会になり、子育ての見直しにもなりました。
専門的な視点で息子の心や発達の状態を捉え直せたことで、はじめて「この子はこういう特性をもっているんだ」と息子の障がいを、本当の意味で受け止められるようになっていったのです。
そのおかげで、息子の見方が変わり、子育ても少しずつラクになっていきました。
職場の方々も我が家の状況を理解してくれていて、みなさん本当に親切で、温かい環境。
しかも、そこは息子と4年以上通っていたこともあり、仕事の流れもすぐに掴めました。
やがて、障がい児の子育て経験が評価され、保護者とも自然に打ち解けていき、担当する親子の数も、少しずつ増えていきました。
上司は、憧れの公認心理師。
短大のころから心理学が好きだったわたしにとって、その存在は単なる上司ではなく、言葉で人を救える “理想の姿” に見えていました。
実際に息子と療育に通っていたときも、その上司の一言に何度も救われた経験があります。
だからこそ、その期待に応えようと、わたしは必死になっていきました。
けれど、期待に応えれば応えるほど、仕事は増えていく一方。
そのたびに胸の奥から「応えなきゃ」「裏切れない」という声が勝手に立ち上がってきます。
止めたいのに止められない。
身体のほうが先に動き、気づけばまた背負い込んでいく。
「ありがとう」が増えるほど、 逃げ道がゆっくり閉じていくような感覚でした。
今回こそ違う生き方をするはずなのに、また同じ罠に吸い込まれていく——
そのことを自分が一番よく分かっていることが、一番苦しかったのです。
そして、毎朝起きることもつらくなり、心のどこかで “辞めるきっかけ” を探していました。
そう思っていた矢先、新型コロナウイルスのパンデミックが起こりました。
「コーチングとの出会い」
緊急事態宣言が出され、仕事も多くの日が休みになりました。
思いがけず訪れた“自分の時間”。
繰り返される悩みに、ほとほと嫌気を感じていたこともあり、再び、夢中で本を読みあさりました。
そして初めて“コーチング”の世界に出会うことになったのです。
あるコーチが、自分の内側を整えるために、ジャーナリングを推奨していました。
ジャーナリングは、その時に浮かんだ想いを、素直に書き出していく習慣。
書き始めると、抑え込んでいた感情が線を引くペン先から次々あふれ出し、止まらなくなりました。
心の中のモヤモヤやザワザワが消えていくのが快感で、気がつけば、一日に何ページも。
コーチングに惹かれ、コーチングを仕事にしている人の本を読むようになりました。
そんなある日、タイトルに惹かれて購入した一冊の本。
『自分の居場所で咲きなさい』(著:川喜田敬)
言葉のひとつひとつが胸の奥にまっすぐ刺さり、深いところが揺さぶられる感覚がありました。
これまでも、悩んだりつまずいたりするたびに、心理学や自己啓発、精神世界の本を開き、そこから気づきを受け取ってきたはずなのに――
心の仕組みや自己探求を続けてきたはずなのに、現実では、同じ悩みを何度も何度も繰り返していました。
その矛盾がずっと重くのしかかっている。
しかし、川喜田敬さんの本を何冊も読み進めるうちに、
「この人なら、現実を変えてくれるかもしれない!」
そう確信を持ち、川喜田敬さんの『コーチ養成講座』へ申し込みをしました。
この出会いが、わたしの人生を大きく変えることになったのです。
「なぜ再び母の元へ戻ったのか」
コーチング養成講座は想像以上に深く、自分のこれまでの思考と、現実で起きてきたことが 一本の線でつながっていく感覚がありました。
講義は毎回楽しくて仕方ありませんでしたが、同時に、これまで避けてきた過去と向き合う時間でもありました。
その中でも最も重い気づきが起きたのは、講座が始まってまもなくのことでした。
しかし、その気づきは誰にも言えず、自分ひとりの胸の内にそっと閉じ込めていました。
――実家に戻る。
それが、わたしの“願い”だったことに気づいたのです。
「母のそばに帰りたかった」
“母の庇護”の中に、もう一度戻りたかったのです。
大好きな母に、助けてもらいたかった。
息子の大変さを、分かってもらいたかった。
ぜんそくの発作の時のように、寄り添ってもらいたかった。
ピアノの時のように、一緒に前に進んでもらいたかった。
その願いは、何よりも強く、そして、何よりも幼かった。
その幼さが――
その執着が――
その依存が――
最悪のかたちで叶えられてしまった。
私は「母のそばに戻る」という願いを、夫の死という代償と引き換えに実現してしまったのだと…
願いはいちばん残酷な形で叶えられることがある。
受け入れがたいその感覚と同時に、
「このままではいけない!」
「なんとかしたい!」
そう心に決めました。
「親孝行vs親不孝」
学びが重なるにつれ、少しずつ輪郭のはっきりした気づきが生まれていきました。
なぜ、虐待してしまうほど息子にイライラしていたのか。
わたしは「息子を育てていた」のではなく、息子を通して “母にとって都合のいい娘であり続けよう” としていたのです。
つまり、
母の期待に沿う = 親孝行
母の期待を外れる = 親不孝
無意識にそう信じていました。
言うことを聞く息子なら
→ 「ちゃんと育ててる=親孝行な娘だと思われる」
癇癪を起こす息子なら
→ 「ちゃんとできない=親不孝な娘だと思われる」
だから息子の行動に腹が立ったのではなく、
「息子の母親であるわたしが、母にどう採点されるか」
そこに耐えられなかったのです。
実際にはその場に母はいないのに、いつも“母の視線”の下で育児をしているような感覚がありました。
息子が暴れるたび、息子に怒っていたのではなく、
“親孝行から外れる自分” に怒りを向けていたのです。
「息子からのメッセージ」
親孝行でいたいわたしは、母の顔色を伺い、母の気に入ることだけを選び続けていました。
そうなってしまうと、自分の感情はなく、「やりたい/やりたくない」という感覚すら麻痺していたのです。
そして、その“対象”はやがて母から上司へと変わりました。
“その人”に認められるために必死になり、自分の気持ちを無視し、“その人”のために頑張り続ける…。
ほめられても、認められても、満たされるのは一瞬だけ。
「もっと認めてもらうために頑張らなきゃ!」
そうやって自分を追い込み、ついには身体も心も壊れる。
目的はずっと「誰かのため」で、自分の気持ちは置き去りのままだったのです。
その一方で、息子は違いました。
息子は、純粋に“やりたいこと”を楽しんでいた。
顔は生き生きし、エネルギーは溢れ、止めても止まらない。
わたしの声なんて届かない。
わたしから見れば、完全なる“親不孝”。
でも、それが本来の姿。
それこそが「ありのまま」の姿。
ただ、自分のやりたいことをやっているだけ。
息子はずっと、わたし自身が本当は生きたかった姿を見せてくれていたのです。
これは、“自分の声を最優先にして生きる” という、ごく当たり前の姿でした。
そして、こういうメッセージを届けるために、わたしの元に来てくれたのでしょう。
「ママ、まだ遅くないよ」
「ぼくみたいに、ママを無視して、親不孝して、やりたいことやりなよ!」
そのメッセージに気づいた瞬間、わたしは心からこう思えました。
「産まれてきてくれてありがとう!!」
息子が、愛おしくてたまらなくなりました。
「息子を愛せなかった理由」
なぜ、身ごもったとき、そして産まれてからも、息子に愛着がなかったのか。
その理由も自ずと分かってきました。
まだ、母離れできていなかったからです。
わたしの心の“いちばん深い席”は、ずっと母で埋められていました。
ずっと母の方を見て生きてきた。
傷ついたときも、苦しいときも、心が向かう先はいつも「母」だった。
だから、
息子が生まれても、心の中に「息子の居場所」がなかったのです。
母にとっての「よい娘」であることを手放せないまま、同時に「息子の母」になろうとした。
その二つの役割が、心の中でせめぎ合っていた。
しかし、わたしはまだ「よい娘」の座に座り続けていた。
愛着が芽生える余白が残っていなかった。
だから、かわいいとも、愛おしいとも思えなかったのです。
「解放のとき」
いろいろな気づきが積み重なったある日、母と大喧嘩になりました。
今までなら感情を飲み込んで終わっていたはずが、その日はブレーキが利かず、すごい剣幕で泣きながら、怒鳴っていました。
母から言い返されても、引き下がらず言い返していました。
その日は、息子と近所のお祭りに行く約束をしていました。
行きたい気持ちはまったくありませんでしたが、息子が楽しみに待っていたので、渋々向かいました。
電車の中でもずっと、母に怒鳴った言葉が、頭の中でリピートし続けていました。
現地は、お囃子と笑い声で賑わうお祭りの空気。
でも、私の気分はどん底。
お祭りは「目の前」でやっているのに、自分は別世界にいるような感覚。
みんなが楽しそうにはしゃぐ姿が、なぜか嫌味のように感じられました。
母に逆らった罪悪感と、「これでよかったんだ」という気持ちが行ったり来たり。
何もスッキリしないまま、その夜はほとんど眠れず、朝を迎えました。
そして朝、突然はっきり思ったのです。
「まだ言い切れていないんだ!」
「今がチャンスだ!全部言おう!」
父にも、全てを知ってもらいたかったので、父と母に座ってもらい、心にしまっていた想いをすべて話しました。
・母のルールに縛られて生きづらかったこと
・子育てで死にたいほど追い詰められていたこと
・自分の人生を見直すためにコーチングを学んだこと
・これからどう生きていきたいのか
父も母も静かに聞いていました。
わたしは、途中から涙が溢れ、声を出すのも精いっぱい。
何度も、もう話すのをやめようかと思うほど、辛い時間が続きました。
母は一度も私の顔を見ようとせず、横を向いたまま。
全てを吐き出し終えたあと、母はしばらく混乱し、俯いたまま…
そして、ぽつり
「私の育て方が悪かったんだね。そんなこと言われたら、ショックだわ」
母の悲しそうな顔を見た瞬間、胸が締めつけられました。
「やはり、母を傷つけてしまった…」
父はため息をつき、その場を離れていきました。
その日一日、心は大きく揺れていました。
「本当にこれで良かったのか…?」
分からなくなるほど動揺していました。
その後しばらく、ぎくしゃくしながらも、母とは何事もなかったかのように生活していました。
ところが、奇跡が起きたのです!
数日後、洗濯物を干しながら、母がふと、
「あなたが頑張ってきたから、(息子も)伸び伸びといい子に育っているのよ。」
その言葉を聞いた瞬間、目頭が熱くなりました。
今まで一度も子育てをねぎらってくれたことがなかった母が、初めてくれた、奇跡のひとこと。
「あのとき、死ななくてよかった」
母の顔色を無視し、自分の気持ちをありのままぶつけ、 “親不孝”をしたことで、一番欲しかった言葉を受け取ることができたのです。
「自然な親子の形」
一連の話を師匠(川喜田敬さん)に話したとき、こう言われました。
「お母さんのことを、かわいそうな人だと見ていませんか?」
その瞬間、はっとしました。
ずっと母に従って生きてきたのだから、母は強い人なのだと思い込んでいました。
しかし、母を傷つけないようにご機嫌をとり続けていたということは、母を 「傷つきやすい弱い人」 だと見ていた、ということに気づいたのです。
けれど、あの日
感情を剥き出しにし、自分の気持ちを初めて素直に吐き出し、言えなかったことを全部ぶつけた。
母を傷つけるような言葉も言った。
それでも母は、わたしを受け止めてくれた。
「母は強い。だったら、私ももう遠慮せずに生きよう」
そう決めました。
それからは、小さな言い合いが増えましたが、それは、遠慮なく“素”を出せるようになった証拠。
ようやく、自然な親子の形に戻れたのだと思いました。
「葛藤の日々」
コーチ養成講座が終盤に差しかかる頃には、すっかりコーチングの魅力に取り憑かれていました。
わずか半年の間に、自分を縛りつけていた“制限”をいくつも見つけ出し、嫌いだった自分を、少しずつ受け入れられるようになっていったのです。
そして、現実もまた、少しずつ変わり始めているのを実感していました。
「コーチングで起業したい!」
「わたし自身が苦しかったからこそ、同じように悩んでいる人のサポートをしたい!」
想いが、大きく膨らんでいきました。
今すぐにも仕事を辞めてしまいたいと思う反面、中途半端で終わらせると迷惑をかけてしまうという気持ちが強く、「頑張って、あと8ヶ月働こう」と決めていました。
その直後、わたしはコロナウイルスに感染。
すぐに復帰するつもりでしたが、1週間たっても、1か月たっても、倦怠感や微熱、息苦しさが続きました。
病院で「後遺症」と診断され、しばらく仕事を休むことに。
そう。
心が限界になると、心や身体に不調が現れる。
まるで“心”が「もう限界だよ!」と言うように、体を止めにきていることは気づていました。
長い時間、わたしの中では苦しい葛藤が続きました。
「辞めたい。もう限界だ」
「でも、今辞めたら迷惑をかける」
「起業したい。今がタイミング」
「いや、まだ形にもなっていないのに」
どちらの声を聴けばいいのか…
倦怠感がひどく身体が動かない中、思考ばかりが活発に動いていました。
何も決められない自分を責めながら、それでも決めきれない——
そんな悶々とした日々が続いていました。
「自分を主人公に」
コーチ養成講座は、すでに修了していました。
講座で学んだ「セルフコーチング」という、自分で自分を導く方法を使って、内観をしてみることに。
すると――
なぜ、職場を辞めたくても辞められなかったのか。
その理由が、少しずつ見えてきたのです。
職場は、主人が亡くなったときに親子で支えてもらった場所。
私はずっと、その優しさに守られて生きてきました。
「恩返しをしなければ!」
「助けてもらった分、犠牲になってでも役に立たなきゃ!」
そう思い込み、無理をして働き続けていたのです。
そして、休職中も園長先生はとても優しく、
「完全に治るまでは、慣らしで来てくれればいいからね」
と何度も気遣ってくださいました。
その優しさが、揺れ動く大きな原因だったのです。
わたしは、“若くして未亡人で、障がいのある子を抱えるかわいそうな人”
→やさしくしてもらえる
この構図にたどり着くことができました。
「その立場を、自分の手で握りしめていたんだ!」
「だから、辞めたくても、旨味があって辞めれなかったんだ!」
そして、さらに記憶がさかのぼりました。
思い返せば幼い頃、
ぜんそくの発作が出ると母がそばで看病してくれました。
発作の苦しさより、背中をさすってもらえる安心のほうが心地よかった。
そのやさしさが欲しくて、無意識に発作を招いていたのです。
それが始まりでした。
“身体や心を壊すことで守ってもらう”
私はずっと、その方法で自分を守っていたのです。
けれど、
「もう”弱い立場”では生きていたくない!」
「自分の人生の “主人公” として生きたい」
心の底からそう思い、そして決めました。
「わたしを主人公にしてあげよう!」
コロナ発症から3か月後、私は園長先生に伝えました。
「辞めさせていただきます」
まるで、身体にまとわりついていた鎖がほどけていくようでした。
そこから後遺症はみるみる回復していきました。
「動き始めた最初の一歩」
仕事を辞めたあとしばらくは、処女作『モンスターママの告白』の執筆に取り組みながら、商品づくりの準備をしていました。
そんなある日、その本を読んだ、かつての幼稚園の後輩から連絡がありました。
「園で講演家を探していて…講演会をお願いできないですか?」
その一言に、心が大きく震えました。
「わたしの書いた言葉が、誰かに届いて、心を動かしたんだ!」
「すごい!こんなことが起きるんだ!!」
嬉しさもありましたが、あまりに大きな話に、思わず動揺しました。
しかし、
「これはチャンスかもしれない!」
園長先生に会いに行くと、講演会の話だけでなく、園で抱えている保育の困りごとをいくつも話してくださいました。
その話を聞きながら、胸の奥で思いました。
「わたしがサポートしたい!」
熱が走りました。
すぐに「保育コンサルティングの企画書」を作ることを決意。
「これまで学んできたことも、経験してきたことも、現場に返せる」
そう思うと、アイデアが止まらないほど湧いてきました。
数日後、完成した企画書を持って幼稚園を訪ね、プレゼン。
結果、一年契約で正式採用が決まりました。
「現実が変わり始めた!!」
胸の奥からじわじわと熱が広がり、自分の選択が間違っていなかったと確信しました。
起業して最初の大きな仕事でした。
「焦りの日々」
保育コンサルは半年後。
そこへ向けて何かしら現実が動き続けると思っていました。
でも、止まってしまった。
SNSを開くと、仲間たちがどんどん進んでいるように見える。
あの頃の私には “全員が前に進んでいて、自分だけ置いていかれている” ようにしか見えませんでした。
そして、まったく知らない人の投稿にまで心がかき乱されました。
「私だって本気を出せばこれくらいできるのに」
「あの人にできて、なんで私は止まってるの」
嫉妬と悔しさがごちゃまぜになって押し寄せ、そこから湧き上がった焦りは、日に日に膨らんでいきました。
「SNS発信なしで、3カ月で月収100万円!」
そんなうたい文句に惹かれて、あるコンサル講座に申し込んでしまったのです。
しかし、蓋を開けてみると、わたしの価値観とはズレていて、結局、2回参加したところで、気持ちは完全に滞ってしまいました。
そんな時、偶然にも師匠から声をかけていただいたのです。
ただの近況報告のような会話だったのに、話しているうちに胸の奥がじわじわ温かくなっていくのを感じました。
他の人の言葉は、心の表面にしか届かなかったのに、この人の言葉だけは “奥” に届く。
理屈ではなく、心が先に反応しました。
「ああ、やっぱりこの人だ!」
私は迷いなく、マンツーマンでの継続をお願いしました。
「焦りの正体」
「自分ビジネスで、もっと結果を出さなきゃ!」
そう思うたびに、胸が焼けるように焦りでいっぱいになっていました。
そこをコーチングしてもらいました。
焦りの正体は、
「わたしは “何者か” にならなければいけない」
でした。
師匠に問われました。
「もし、何者かにならなかったら、何が起きると思っているのですか?」
その問いから、ひとつの記憶が浮かびました。
小学6年のとき、卒業式で弾く「仰げば尊し」の伴奏者に立候補しました。
今振り返ると、動機は、弾きたかったからではありません。
見返したかったのです。
成績もふつう。運動もできない。
同じ地区の“神童”たちによく笑われていました。
「平均点、下げるなよ」
そんな言葉を浴びせられたこともあります。
悔しかった。
負けたくなかった。
でもその奥には、もう一つの願いがありました。
母に胸を張らせたかった。
そして、母にもっと認めてもらいたかった。
しかし、本番、緊迫した雰囲気にのまれ、緊張で指が震え、息も浅くなり、演奏は乱れました。
式のあと、聞こえてしまったひそひそ声。
「伴走者は、〇〇ちゃんの方がよかったよね」
その言葉が胸に突き刺さり、大きなショックを受けました。
「わたしは代表になる器じゃなかった」
「立候補なんて、しなきゃよかった」
「母をがっかりさせてしまった…」
その悔しさと虚しさは、ずっと心の底に残っていたのです。
そして今――
「早く結果を出さなきゃ」
「成功していないと思われたくない」
そう焦っている自分と、あの日の自分が重なりました。
わたしは今もなお、母に認められる“何者か”にならなければ、存在価値がないと信じていたのです。
師匠は言いました。
「あなたは、あの時に手を挙げた自分を、周りと一緒になって今も否定し続けているのです」
「その子に、今のあなたが味方になれるとしたら、何と声をかけますか?」
すぐには言葉が出ませんでした。
しかし、
「息子に対してなら、わたしは何と言葉をかけるのだろう?」
そう思った瞬間、自然と言葉が溢れ出てきたのです。
「 誰も手を挙げない中で手を挙げた勇気、すごいよ」
「練習してたの、ちゃんと知ってるよ」
「歌いやすく丁寧に弾こうとしていたよね」
「 弾けない人に批判する資格はないよ」
「あなたはやり遂げたよ」
その言葉は途中から、 息子に向けてではなく “35年前のわたし” に向けられていました。
その瞬間、あの日の出来事が初めて塗り替わりました。
焦りの根っこはこうでした。
「母に認められるために、何者かにならなければいけない」
その恐れが、今のわたしに、「走れ」「証明しろ」と叫び続けていたのです。
そしてこの声は、幼い頃からわたしの中に棲みつき、頭の奥で、絶えず「もっと」「まだ足りない」と叫び続けていました。
ピアノも、保育士も、インテリアコーディネーターも、
妻になっても、母親になっても――
すべては“認められる何者か”になるための証明をしようとしていたのです。
けれど、その証明が生み出したのは、満たされることのない虚しさと、終わりのない焦りだけでした。
「息子という存在が教えてくれたこと」
そして、さらにもうひとつのことに気づきました。
「何者かにならなければいけない」という呪縛を外しに現れた存在が、息子だったことに。
「何者かにならなくても、生きていていい」
「出来なくても、そこにただいるだけで、十分に愛される」
その価値観を、息子は “生きて見せる” ことで教えてくれていたのです。
息子は、なぜか昔から人に好かれる子でした。
療育施設では先生たちが、「ほんとにかわいい」と頬をゆるませ、
通っていたママたちからも、「見てるだけで癒される」と言われ、
「いるだけで明るくなる子だね」と 何度も言葉をかけてもらいました。
今も学校やデイサービスでは人気者で、息子が休むと寂しがる子が何人もいると聞きます。
正直、息子は “できないこと” だらけです。
4歳まで言葉は一語も出ず、
癇癪ばかりで先生たちは手を焼き、
今は重度の知的障がいで知的年齢は3歳ほど。
それでも——
息子は、「そこにいるだけ」で愛される。
そして、わたしも、息子がそばにいてくれるだけで、幸せを感じています。
“優秀じゃなくていい”
“できないことばかりでいい”
“ただ、いてくれるだけでいい”
今は心から、そう思えています。
わたしがずっと信じてきた
“ できる人間が価値ある人間 ”
“ 何者かにならなければいけない ”
という価値観は、息子の存在によって、ひっくり返されていきました。
「初めての講演会」
そうこうしているうちに、自分ビジネスとして最初の仕事、「講演会」が近づいてきました。
テーマは、わたし自身のライフストーリー。
子育てのこと、主人の死と向き合ったこと、そして、そこからどう立ち上がってきたのか。
正直、不安でした。
「ほんとうに、わたしでいいの?」
「ただの主婦で、起業したばかりなのに?」
「こんな話、誰が興味もってくれるの?」
怖さはありました。
それでも、どこか奥のほうで自信もありました。
「これはわたししか語れない話だ!」
そして迎えた当日。
会場には、次々に人が席につき始め、そのざわめきの中で、自分の鼓動がはっきり聞こえるほどでした。
手のひらにはじんわりと汗。
「始まるんだ…」という現実を目の前にして、わたしは深く深く呼吸を繰り返しました。
ただ整えることに専念しながら、胸の内で何度も言い聞かせる。
「大丈夫」
「わたしならできる」
いざ話し始めてみると、心の奥から“火”がつくような感覚がありました。
原稿どおりの内容を話しているはずなのに、言葉が“頭”ではなく、“心の底”からあふれ出してくるのを感じました。
息子に怒鳴ったこと。
感情を抑えられず、手を挙げてしまったこと。
どうしようもない絶望の中で、「もう生きていたくない」と思ってしまったこと。
――“きれいな母親像”なんて、どこにもなかった。
それでも、
その全部をさらけ出すたび、うなずきながら、じっと話を聴いてくれる人達もいて、会場の空気が少しずつ、やわらかくなっていくのを感じました。
わたしは思いました。
「“何者か”にならなくても、 “ありのままのわたし”でいいんだ」
失敗も弱さも、語っていい。
誰かに笑われても、評価されなくても、それが“生きている証”なんだ。
講演が終わってもしばらく、胸の高鳴りは収まりませんでした。
誰のためでもなく、自分の声で、自分の人生を語った時間。
講演が「成功」だったかどうかは正直わかりません。
もうそんなことはどうでもよかった。
会場を後にして、しばらくの間、体の内側から「満たされている」のがわかりました。
「やりきった」
「わたし最高」
「生きててよかった」
そう思えている自分が愛おしくてたまりませんでした。
講演が終わったあと、一人の女性がそっと声をかけてくれました。
「実は、わたしも同じ思いをしていて……」
その一言に、胸の奥が熱くなりました。
あのとき語った“弱さ”が、誰かの心に届いたのだと思うと、体の奥から、あたたかいものがこみ上げてきました。
「やりたいことが分からなかった理由」
ここまでコーチングを重ね、わたしは随分と軽くなっていきました。
仕事はもちろんプライベートも「自分のやりたいこと」を優先できるようになったのです。
たとえば、息子を母に預けて外食に行ったり、思い切って旅行に出かけたり…
今までのわたしなら、決してできなかったことです。
けれど、母の機嫌が目に見えて悪くなってきたのです。
まるで、足を引っ張るように…。
「まだ何か、わたしの中に見つめ直すものがあるのか…」
そう思い、師匠に見てもらうことにしました。
母が不機嫌になる
→ 「母を不機嫌にさせないこと」が最優先になる
→ わたしは機嫌を取ろうとして、やりたいことをやめる
つまり、今もなお、自由に生きることを無意識に止めているという構図が浮かび上がってきたのです。
機嫌を取らなければいけない。
やりたいことは我慢しなければいけない。
自分だけ楽しんではいけない。
そう思わせている「何か」が、確かにある。
そのとき、頭の中に浮かんだのが「弟のこと」でした。
この話は、口にするのも苦しくて、ずっと奥にしまい込んでいたものです。
中学のとき、ふとした流れで部活の友達に、弟の話をしたことがありました。
ほんの少し、打ち明けただけでした。
けれど翌日、別の友達から聞かされました。
「人殺しって、噂になってるよ」――と。
頭の中が真っ白になりました。
何がどう伝わったのかも分からず、ただ全身が硬直して、後悔だけが残りました。
「話さなきゃよかった」
「弟のことを口にしてはいけない」
そう心の奥に深く刻まれたのです。
それ以降、「人殺し」という言葉が頭から離れませんでした。
「多分、わたしがあのとき、弟を押したんだよな…」
そう思うと、生きていることが申し訳なくて、罪悪感がこみ上げました。
あのとき自分がしたことが、どこまで影響したのかは分からない。
でも、 “自分のせいで” という感覚だけは、消えませんでした。
しかし、逃げずに話す時が来たのだと腹を括り、涙を流しながら、言葉に詰まりながら、全てを話しました。
話し終えると、師匠は静かに言いました。
「自分のせいで、お母さんを悲しませてしまったと思ってるんですね」
「ずっと、お母さんを苦しめないように生きてきたんですよ」
「だから、自分だけ楽しんではいけないと思っている」
その言葉が、今までの苦しみを消し去ってくれるかのようで…
――そうか。
わたしは、母を苦しめないように生きてきたのか。
胸に染み込んで、しばらく、涙が止まらなくなりました。
そして、思い出したのは、短大時代のことでした。
いつもひとりだった2年間。
あの孤独は、「仲間に馴染めない」のではなく、「馴染んではいけない」と、どこかで自分に禁じていた。
わたしは、自ら孤独を選んでいた。
だから、いつも、楽しいことをしていても、やりたいことをやっていても、
「これ以上、自分だけ楽しんではいけない」
そうやって無意識にブレーキをかけてしまっていたのです。
そして、母に認められる選択をしようとしていた。
母の期待を裏切れなかった。
“母のための人生” から抜け出せなかった。
――そして、やりたいことをやっていても、途中で見失う。
これが、「やりたいことが分からなかった」根っこでした。
「ああ、やっとここに辿り着いた……」
“弟との辛い思い出”と“やりたいことが分からない”
このふたつが繋がった瞬間、長年心に溜まっていたものが、すーっと浄化されていくのを感じました。
その後、不思議と母の機嫌が良くなっていったのです。
「今、やりたいことをやる」
講演会を皮切りに、各クラスを巡回して担任の先生へ助言をしたり、職員向けの研修を担当する仕事が広がっていきました。
さらに、ご縁がつながり、子ども部屋の改造&整理整頓講座のご依頼、そして高額の継続コーチングセッションのお申し込みもいただきました。
どれも「楽しくて仕方がない」と思いながらできています。
努力している感覚がないのに感謝される。
無理をしていないのに成果が出る。
身を削らずに、自然にできてしまう。
昔のわたしなら、信じられない現実です。
努力も犠牲も覚悟も捧げてやっと報われる——
それが“正しい生き方”だと信じて疑わなかった私が、今は「ただ好きでやっていること」で喜ばれ、感謝され、お金までいただいている。
こんな未来が自分に訪れるなんて、あの頃のわたしには一ミリも想像できませんでした。
なぜこんな変化が起きたのかといえば、わたしはもう “母の喜ぶ選択” ではなく
“わたしがやりたい選択” をしているからです。
そう、まるで息子が、
「やりたいからやる」
「やりたくないことはやらない」
ただそれだけで輝いているように。
わたしも今、“やりたい” を基準に生きることを自分に許したのです。
そして、もうひとつ「やりたい」と感じたことがありました。
それは――ピアノを弾くこと。
ずっと封印していたピアノに、また触れてみたいと思ったのです。
弾きたい曲の楽譜を買い、 昔のように指は動かないけれど、一音一音を確かめるように、ゆっくりと鍵盤に触れています。
“上手に弾こう”ではなく、 “曲を味わおう”と思えるようになりました。
あの頃、母に認められたくて必死に弾いていたピアノを、今はただ、自分のために弾いている。
最初にオルガンが来た時のような、心がふわっと弾む感覚に戻っていくのを感じています。
「親不孝が、わたしを生き返らせた」
親の声ばかりを聞き、親を喜ばせるように生き、“孝行娘”であることに必死だった頃、
わたしはずっと「やりたいことが分からない」人間でした。
けれど、自分の声を聞き始め、はじめて“親不孝”をした瞬間、わたしはようやく自分の人生のハンドルを握り直しました。
やりたいことは「探すもの」ではなく、封じ込めていた自分を解放したときに、自然と立ち上がってくるものだったのです。
今、わたしは “やりたいこと” を仕事にしています。
それは特別な才能を得たからでも、資格を取ったからでもありません。
ただ、自分の声に従うことを自分に許しただけでした。
講演で自分の人生を語る時間も、誰かの人生に寄り添うコーチングも、園で子どもや保育士さん達と関わる仕事も、子ども部屋改造&整理整頓講座も、
「母に喜ばれる選択」ではなく、「わたしがやりたい選択」として、選んでいます。
評価されるためでもなく、正しさを証明するためでもなく。
その感覚は、かつて必死に掴もうとしていた「何者かにならなければ」という生き方よりも、ありのままの自分で生きる方が、はるかに楽で、そして楽しいです。
そして、この本は、かつてのわたしのように「親の期待の中で生き、苦しんでいる人」に届けたい。
親を喜ばせるための人生をやめたとき、人は初めて “自分として” 生き始める。
そのことを、わたしは自分の人生で証明しました。
だから今、その証明として、この本を書くという「わたしのやりたいこと」をこうしてやっています。
これまで誰にも“全部を”語ったことのない、心の奥に眠っていた物語です。
断片的に話したことはあっても、こうして一つの流れとして書くのは、初めてのことでした。
正直、書きながら何度も苦しくなりました。
けれど、不思議なことに、その痛みを言葉にするたび、エネルギーがあふれて、書くことを止められないのです。
まるで、長いあいだ閉じ込めていた自分自身が、「やっと、外に出られた」と喜んでいるように。
苦しく、辛い過去があったからこそ、いまの幸せをこんなにも深く味わえるのだと思います。
あの時間さえ、もう否定ではなく“ありがとう”と言える。

主人が亡くなって7年が経ちました。
確実に自分の人生を切り開き、息子と一緒にしあわせの階段を昇っています。
ふと立ち寄ることができる場所、悩んだら駆け込むことができる場所
それが
「まめこのおうち」です。